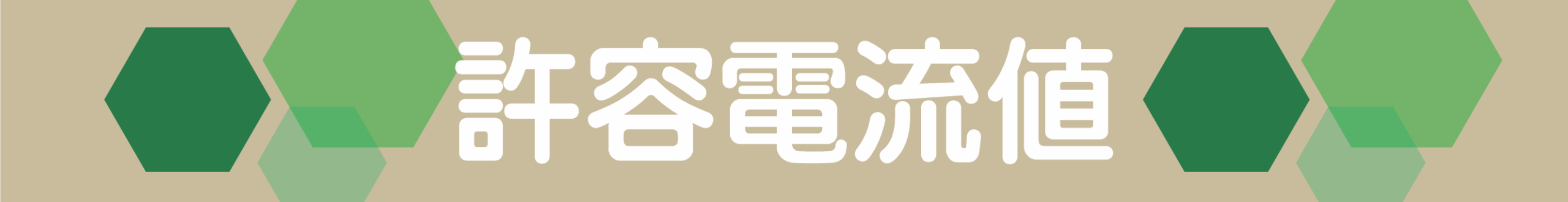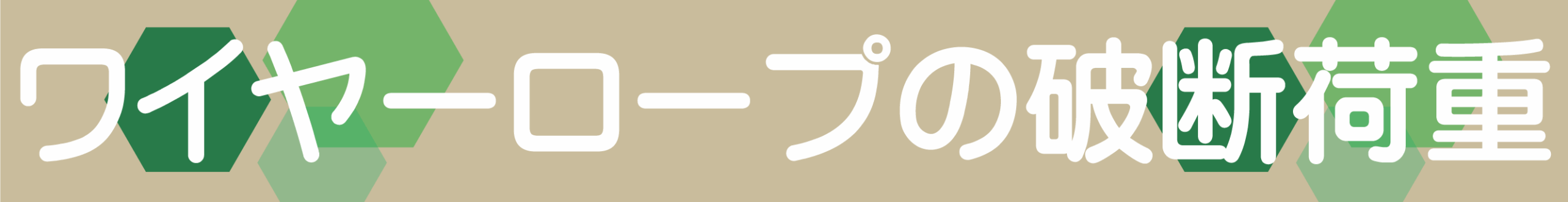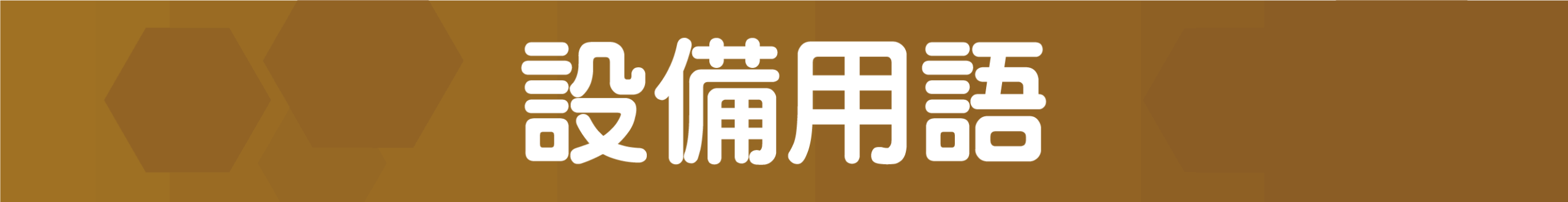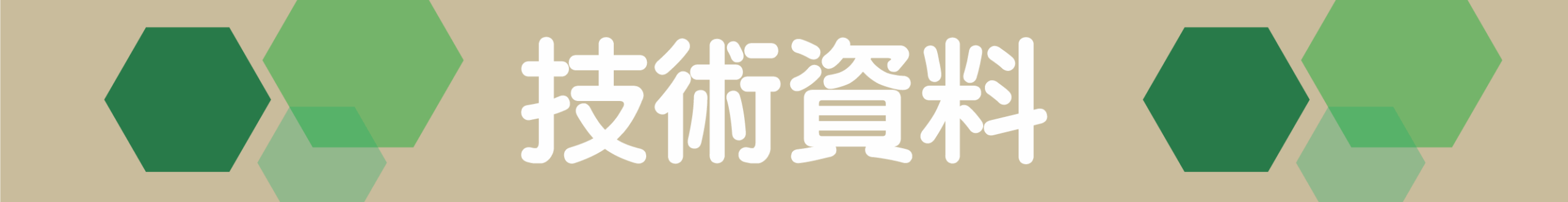鎌倉時代の庭園(かまくらじだいのていえん)とは|造園用語
鎌倉に幕府が開かれても文化の中心はいぜんとして京都にあったこともあり、鎌倉武士の進出とともに興隆した禅宗寺院も、その庭園は平安時代の尾をひいて浄土式の庭園を設けていた。新しい庭園形式を創造したか否かで判断すれば、この時代は日本庭園史上低調期とされる。ただ後世の庭園に多大の影響を与えた名園を造った夢窓疎石(むそうそせき)の存在は特記されなければならない。夢窓の庭園観は「夢中問答集」に明らかだが、その作庭法の特徴は景(けい)と境(きょう)の巧みな構成にある。庭園内に、それぞれひとまとまりのイメージをもつ局部構成、例えば10か所を選んで周遊園路の途中に組み込み、これを十境と呼ぶ。十境は、境内から望見できる富土山あるいは代理富士などの景と一体となって、平安時代に比べて狭小化し傾斜地立地の鎌倉時代庭園を効果的なものとした。夢窓作の庭園は天龍寺・永保寺・瑞泉寺、それに夢窓命名の西芳寺十境、南禅寺十境が著名である。なお庭園ではないが、禅宗寺院の伽藍配置は、鎌倉時代から室町時代にかけての敷地計画史上特筆されるものである。→いしだてそう
鎌倉時代の庭園|か|造園用語集用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
鎌倉時代の庭園とは造園用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「E...