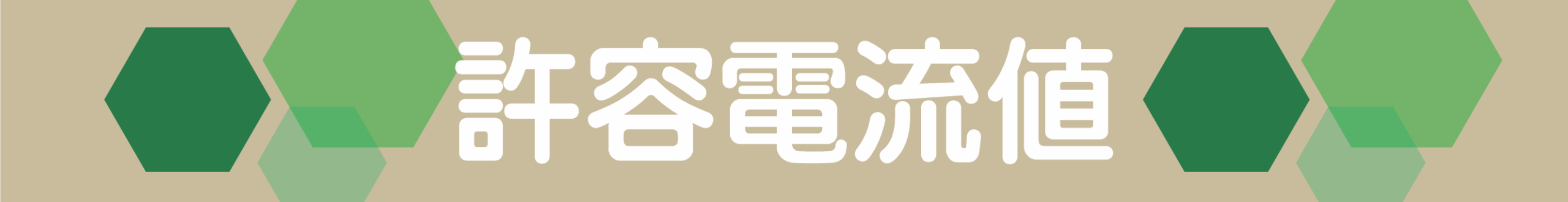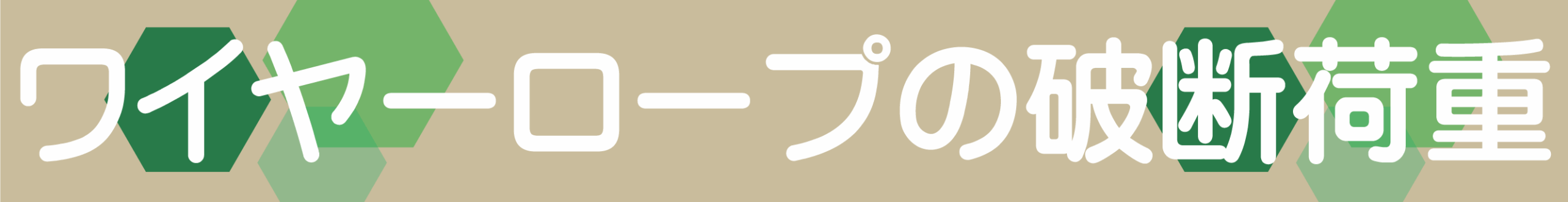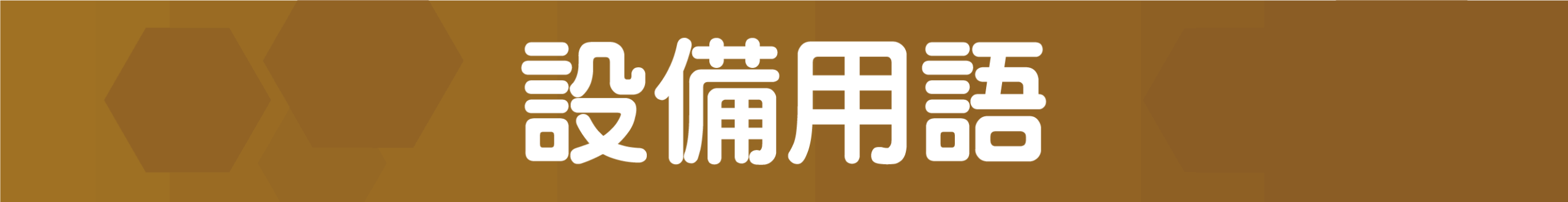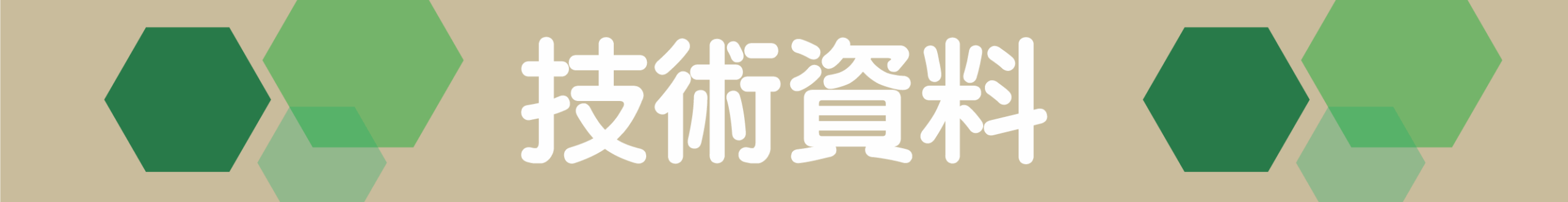環境保全計画(かんきょうほぜんけいかく)とは|造園用語
「環境保全」とは、人増を環境に依存した存在として位置づけ、人間の諸活動によってもたらされる弊害を防止し、また自然に積極的に働きかけて、人間やその他の生物の生存環境が最良の状態になるように維持管理していくという、総合的、積極的、操作的概念であり、その目標や方法、制度等を体系的に明確化し、それを実施していくための計画。「環境保全」(environmental conservation)は、「環境保護」(environmental protection)、「環境保存」(environmental preservation)と一連の概念をなす用語である。「環境保護」は原生自然など自然環境そのものを開発などの人為から守るという環境の側に立った概念であり、「環境保存」もある特定の環境を手を付けずに保存していくという場合に用いられる。国レベルの制度や施策におげる目標や方針を定めたもののなかで、自然環境を主体とするものに「自然環境保全基本方針」(1973(昭和48)年)があり。「自然環境保全法」第12条に述べられている。この中では、人間生活にとっての自然環境の位置付けや、自然環境保全政策の基本的態度、都市・農山村・原生自然といった国土全体の多様な自然環境に対応する各法制度の体系的な位置付けと運用が示されている。また1977(昭和52)年には、これをより具体化し、ほぼ10年後の政策目標とする「環境保全長期計画」(1977年)が環境庁によってまとめられている。ここでは達成すべき自然環境の「質」と「量」が示されているほか、公害防止についても、それに要する費用が明らかにされている。一方、環境の資源的利用の側面から、あるいは生活基盤整備という視点から環境保全をとらえたものに「国土利用計画法」(1974年)がある。特に「土地利用基本計画」では、都市地域・農業地域・森林地域・自然公園地域・自然保全地域の5地域区分が示され、それぞれ「都市計画法」、「農業振興地域の整備に関する法律」、「森林法」 、「自然公園法」、「自然環境保全法」等の上位計画となり、利用と保存の調整が図られている。こうした国レベルの制度以外に、自治体レべルにおいて、各種の「環境影響評価条例」、「公害防止条例」、「自然保護条例」、「景観条例」等が定められている。環境保全計画の方法については、いまだ完成されたものはないが、様々な検討がなされている。制度にかかわるものとして、例えば「環境保全水準」や「環境容量」の設定、「環境モニタリング制度」や「環境アセスメント制度」の技術上・手続上の検討などが挙げられる。また具体的な空間を対象とした計画手法としては、昭和40年代に紹介されたマッ クハーグ(I.L.McHarg)らの土地利用計画手法をはじめとして、わが国の環境や風土に応じた各種の計画手法が提案されている。また近年においては、景観を主体としたアメ ニティ(快適性)への要求が高まり、それらの保存・創出も環境保全計画の一環として重要な地位を占めてきている。