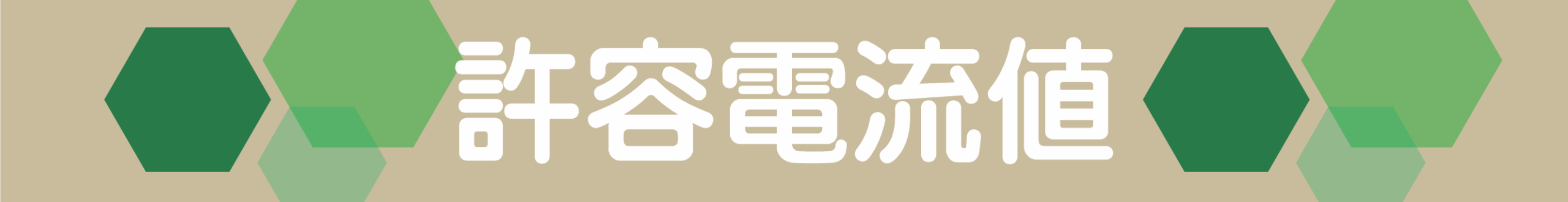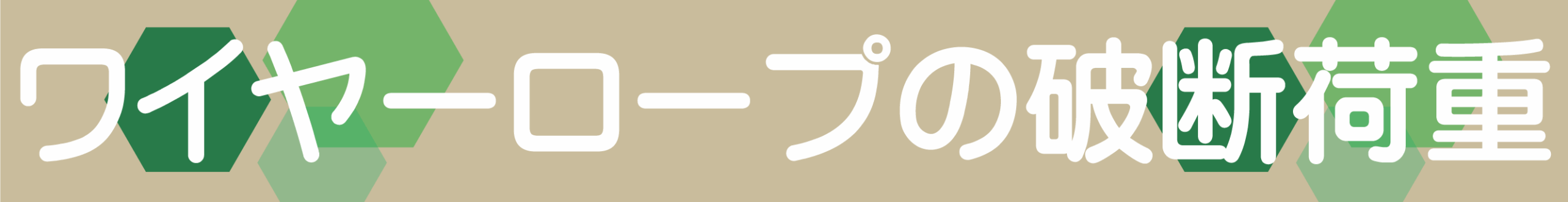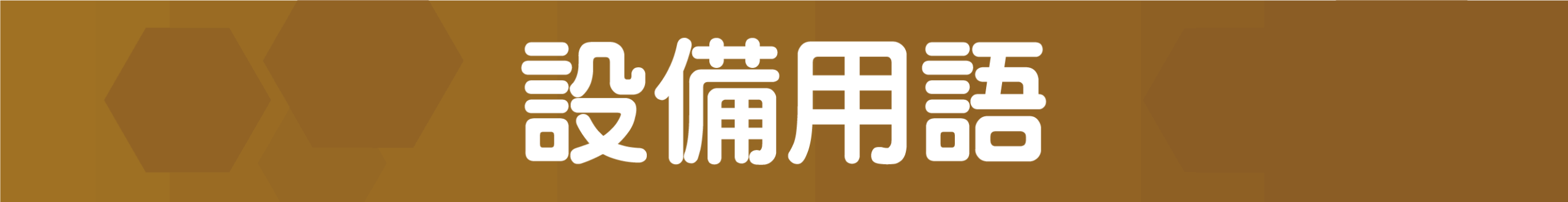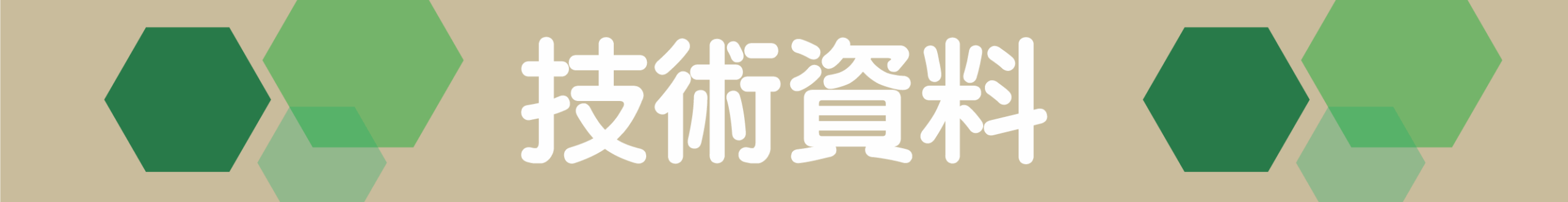緩衝緑地(かんしょうりょくち)とは|造園用語
工業地帯や高速道路、鉄道、飛行場の場合に代表されるように、それぞれの機能空間内部から発生する騒音、娠動、粉塵が、そこに隣接する住居地域等の機能空間に伝播し、いわゆる公害による悪影響を拡散させないための区切りとしての緑地帯や公園緑地。緩衝緑地は、主に産業公害対策の地域的予防措置として着目され、公害発生の恐れが多い臨海工業地帯において工場群と後背住宅地域とを分離、遮断することを目的として設けられることになった。 わが国にあって緩衝緑地が制度化されたのは、1965(昭和40)年制定の「公害防止事業団法」において、共同福利施設のーつとしてこれが規定されたことに始まり、1971(昭和46)年には、都市公園体系の中に公災害対策緑地として緩衝緑地が位置づけられた。また1974(昭和49)年に成立をみた「都市緑地保全法」は、無秩序な市街地化の防止、公害または災害の防止等のために必要な遮断地帯・緩街地帯等を都市緑地保全地区として定めることができるとしているが、これは緑地保全の手法をもって緩衝緑地を形成しようとするものである。さらに、1976(昭和51)年に改正をみた「都市公園法」の兼用工作物規定によるなら、例えば、幹線道路に設けられる道路環境施設帯と一帯となった緑地の設置および管理が可能となり、道路と公園が共同して公害の防止緩和はもとより、地域環境の改善に資するような緑地を形成することが可能となった。これなども緩衝緑地のーつといえよう。公害防止事業団が造成した緩衝緑地を事例的に見ると、千葉県市原工業地帯には、運動公園21.5haを中核とする全面積41.1haの緩衝緑地があり、大分・鶴崎工業地帯の鶴崎地区にも共同福利施設としての緑地が大分石油化学コンビナート地区を遮へいする形で造成されている。これらの緩衝緑地計画例から明らかなように、緩衝緑地は、そもそも緑地が有する存在効果に対応してその設置がなされるものであるが、それに加えて工業地帯で働く人々の各種レクリエーション利用を受け入れる役割、すなわち緑地の利用効果も果たしているのである。工業地域の環境を保全し、快適な地域づくりに資する造園計画法としては、工場敷地レベルでの工場緑化はもちろんとして、インダストリアルパークという概念もあるが、この緩衝緑地は土地利用計画のレベルに対応した緑地帯として位置づけされる。