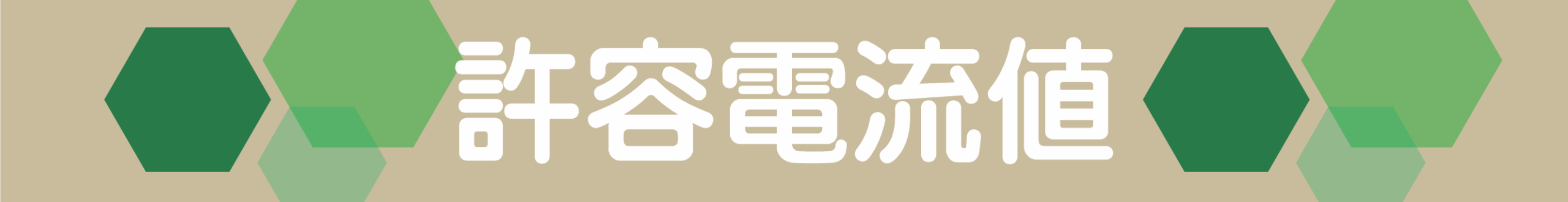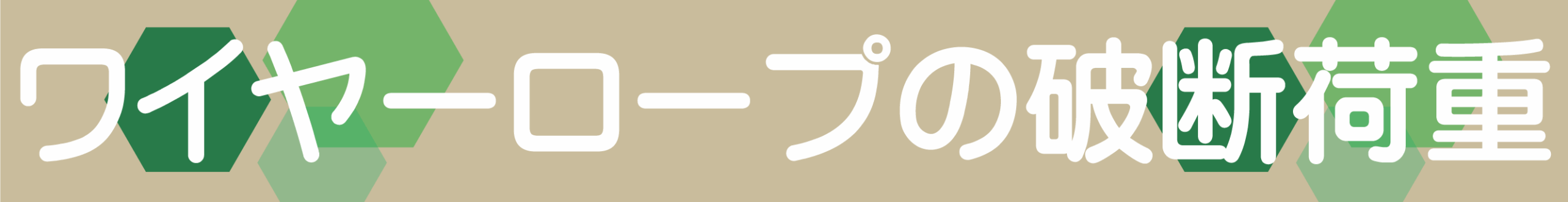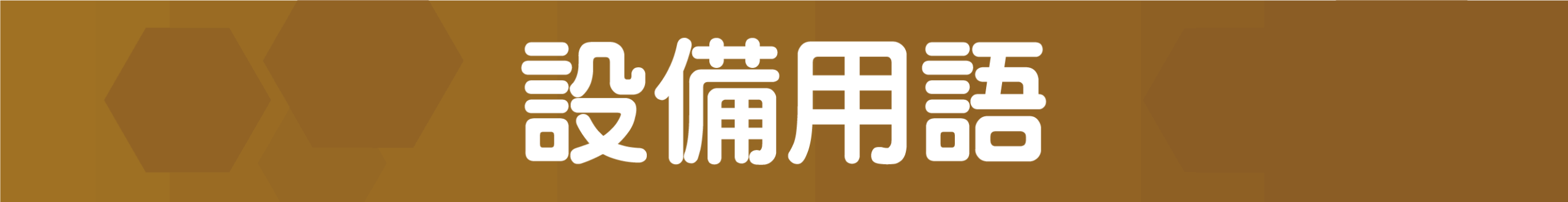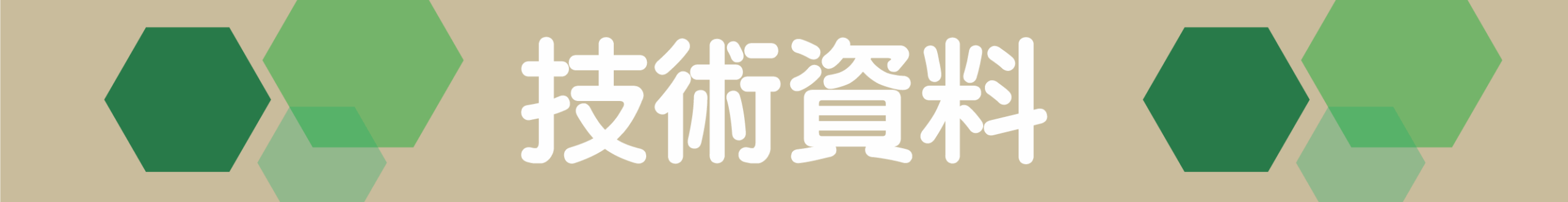交流型農村(こうりゅうがたのうそん)とは|造園用語
都市と農村との交流を軸に、地域振興を図ろうとする農山漁村のこと。過疎地域に多い。これらの地域では、資金や人材、流通手段といったものの不足が最大の悩みになっており、経済が低迷する大きな要因でもあった。一方、大都市においてはその発展と引替えに、豊かな自然やふるさと、人情味あふれる付合い、といったものを失ってきた。こうしたお互いの不足部分を交流によって補完しようという意図で始められたのが都市と農村の交流である。この動きは、なんとか活性化の道を開きたいとする農山村側から積極的に進められた。昭和40年代後半に起こったいわゆる「ふるさと運動」の広がりにより、交流型農村の数が大幅に増加した。交流の形式は様々であるが、最も典型的なものは、東京都世田谷区と群馬県川場村との間に見られるような自治体同士の縁組関係である。国土庁においても1974(昭和49)年に「都市と農村の交流による協同モデル事業」を実施し、こうした動きを推進してきた。自治体間の交流以外にも不特定多数の都市住民を相手にした「ふるさと村」やそれに類似する制度をとっているものが多い。→ふるさとむら
交流型農村|こ|造園用語集用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
交流型農村とは造園用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサ...